ドイツの国旗
国家の一番の象徴である国旗。日の丸、星条旗、ユニオンフラッグ、五星紅旗などがありますが、さてドイツの国旗は、黒赤金旗-Schwarz-Rot-Goldという愛称があります。今回は、ドイツの国旗についてお伝えします。


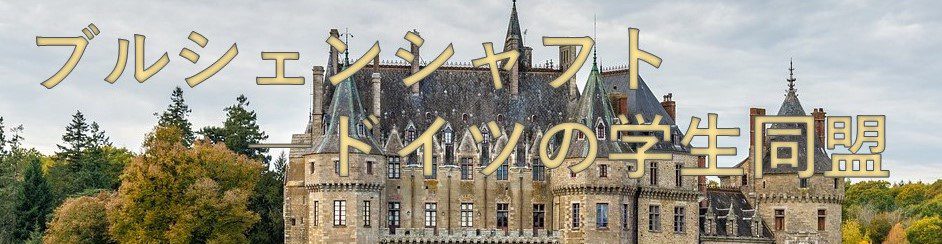
サークルや部活など、日本の学校生活の中で結成されるグループ組織はドイツには存在しません。運動系のクラブは教育機関から独立したスポーツクラブ(Sportverein)がその代わりと言えます。しかし、ドイツには独自の歴史によって成立した学生同盟―ブルシェンシャフト(Burschenschaft)というものが存在します。19世紀前半に誕生したこの同盟は、近代の様々な歴史的変動や制圧を乗り越えて今日も存在しており、同盟内の規則はかなり独特で、真剣を使った「決闘」までも存在するそうです。

ブルシェンシャフトによるヴァルトブルクの祭典(1817)が行われたアイゼナハ近郊のヴァルトブルグ城

In Deutschland ist der Valentinstag ein Tag für Paare, an dem in der Regel der Mann seiner Partnerin ein Geschenk macht. Häufig sind es Blumen. Pralinen und Süßigkeiten werden auch verschenkt.
In Japan gibt es andere Tradition zum Valentinstag, die für Deutsche eher ungewöhnlich sind.
ドイツのバレンタインデーは、カップルや夫婦のための日で、男性がパートナーにプレゼントを贈るのが一般的です。花束をプレゼントすることが多いですが、その他にもプラリネ(ローストしたナッツ類に砂糖を焦がしたキャラメルを加えてペースト状にしたものをフィリングとした一口サイズのチョコレート)やスイーツも贈られます。
日本にもバレンタインデーはありますが、その習慣は、ドイツ人にとってはあまり馴染みのないものです。

ドイツのサービスに関して揶揄される「サービス砂漠」ということばをご存じでしょうか。スーパー、小売店、レストランといった接客業のみならず、電話会社、交通機関を使用する際などに受けるあらゆるドイツのサービスは、不親切なことも多く、営業時間の短さも相まって、良い評判は少ないのが現状。今日はそんなドイツのサービス事情についてお伝えします。

以前ドイツのテレビ事情についてお伝えしましたが、今回は実際のテレビ番組についてお伝えいたします。チャンネルの数は?受信料ってあるの?そしてどんな番組が好まれているの? などの疑問にお答えします。

ウィーンのカフェ文化は日本の茶道と共通点が多いと思います。茶道は、ただお茶を飲む事だけではなく部屋の雰囲気から茶碗などの茶道具の形まで全てが茶道の要素ですね。茶道のほうが間違いなく淑やかですが、ウィーンの「カフェーハウス」(Kaffeehaus)も、飲食はただ一つの要素に過ぎず、カフェの雰囲気、家具、ウエイターなどもカフェーハウスを構成する重要な要素です。ウィーンのカフェ文化は、2011年にUNESCO無形文化遺産に登録されました。保護されているのはコーヒーの作り方や建物などではなくて、「カフェーハウスクルトゥーァ」(Kaffeehauskultur)つまりウィーンのカフェの文化です。

現在、世界には「エンペラー」(皇帝)と呼ばれる人物が一人だけ存在します。それは日本の天皇です。天皇は現在では政治的な意味合いを持たない儀礼的な活動(国事行為)のみを行い、国政に関する機能を有しません。日本国民の大半は、現在の徳仁天皇に対して好意的ですが、なかには批判的な声もあります。

クリスマスが近づき、街もイルミネーションが綺麗な季節になりました。クリスマスに欠かせないアイテムといえばクリスマスツリー。ドイツでは本物の木を飾るのが一般的ですが、近年は人工の木で間に合わせる家庭も多いそうです。
さて、このクリスマスツリー、キリスト教文化のひとつ…と思いきや、元々はキリスト教とは無関係であったのをご存じでしたか?そして最初にツリーの風習が根付いたのはドイツ(当時の神聖ローマ帝国)においてでした。

Wolfgang Ambrosというオーストリアのポップロックミュージシャンが1976年に発表した彼の代表作「Schifoan」という曲の中に「Schifoan is des Leiwandste, wos ma si nur vurstö’n kann♪」という歌詞があります。『スキーするのは想像できることの中で一番楽しいことさ』という意味で、オーストリア人のスキーに対する熱い想いを代弁しています。スキーはサッカーの次にオーストリアの国技だと言えます。でも正直に言うと、サッカーは人気があっても、他の国と比べてあまり強くありません。でもスキーは、実力の点でも世界最高であり、オーストリアの右に出る国はいないと言っても過言ではありません。