家も自分で建てる!? DIY大国ドイツ
目次
ドイツはサービス砂漠と揶揄されることもありますが、その反動なのか国民性なのか、なんでも自分でやろう!という精神が強く、DIYもごく身近に行われています。身近な家具のペンキ塗りに始まり、車の修理、電話の配線工事、さらには自分の家の庭に、新しい家を一から建てている人を見たこともあります。

目次
ドイツはサービス砂漠と揶揄されることもありますが、その反動なのか国民性なのか、なんでも自分でやろう!という精神が強く、DIYもごく身近に行われています。身近な家具のペンキ塗りに始まり、車の修理、電話の配線工事、さらには自分の家の庭に、新しい家を一から建てている人を見たこともあります。

目次
先日、パラグアイ人の知り合いから、南米ではスペイン語が共通言語になっているにも拘らず、それぞれの国で「バス」の呼び名が異なるという興味深いお話を聞きました。
実はドイツ語圏でも同様な傾向があり、国によっては乗り物の名前が大きく異なる場合があります。
中でもスイスドイツ語では標準ドイツ語と語源の違う様々な名称が使われているので、ドイツ人やオーストリア人がその意味を理解することができず、混乱することも少なくありません。
したがって、今回はスイスドイツ語と標準ドイツ語の差異が最も鮮明に表れている乗り物について学んでいきましょう。

目次
赤ずきん、ヘンゼルとグレーテル、ブレーメンの音楽隊。。。子供時代に慣れ親しんだ物語の数々ではないでしょうか。このような物語、いわゆるメルヘンと聞いてどのようなイメージが浮かびますか?夢のようなおとぎ話、森の中に住む魔女、ヨーロッパのふるいお話など様々なイメージがあるかと思います。これらは主にドイツの民話であり、古くから伝えられている物語です。ドイツの観光ツアーにおいては、メルヘン街道というものもありますね。今回はこのメルヘンについてお届けします。
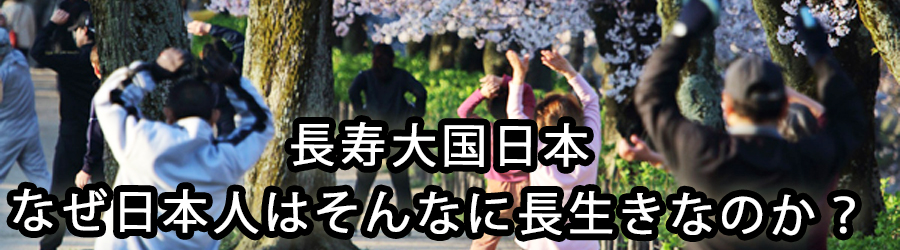
目次
日本の平均寿命は84.2歳と、ドイツの平均寿命80.6歳よりも高くなっています。沖縄県の女性の平均寿命はさらに高く、86歳です。長寿の理由は一体どこにあるのでしょうか?日本人の遺伝子か、日本の健康保険制度か、あるいは生活習慣でしょうか?
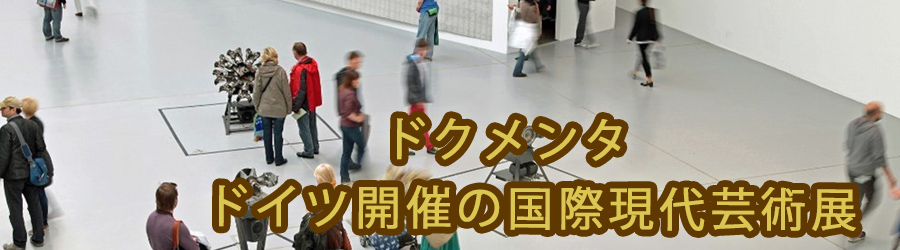
目次
芸術の都といえばパリ。音楽の都といえばウィーン。しかし今日ではそのような認識も徐々にアップデートされている現状があるのではないでしょうか。ドイツでは、5年に一度、カッセルでドクメンタという世界最大規模の国際現代芸術展が行われています。会期中には、人口20万人の都市であるこのカッセルに欧州全土から約60万人の観客が集まるほどです。今回は芸術の祭典となるこのドクメンタについてお伝えします。

目次
オーストリアの学校では9月から新学期が始まりました。私は子どもの頃からこの時期がとても好きでした。季節が変わり、友人にまた会えて新しいノートとペンを買って、何か新しい事が始まるみたいなワクワクする気持ちが湧いてきます。日本の子どもたちも4月には、こんな気持ちになりますか?各国による学校教育制度には意外と大きな違いがあり、オーストリアと日本もそうなので、今回はオーストリアの教育制度をご紹介します。
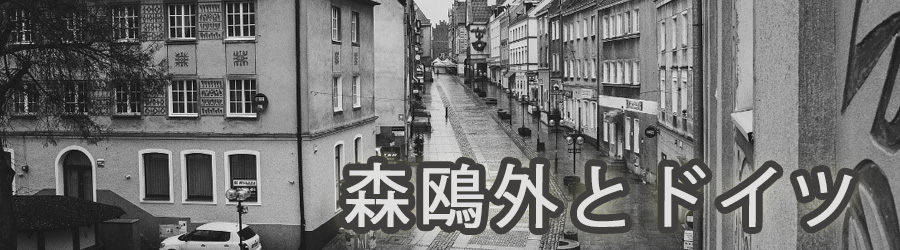

目次
今まで何度かにわたり、スイスの名所をご紹介させていただきましたが、それらは何れもスイスを代表する、言わば定番の都市ばかりでした。
しかし、観光ツアーにまず含まれることがなく、ガイドブックに掲載されることも稀でありながら、実は他のどの都市よりもスイスを代表する場所が存在します。
それがシュヴィーツなのです。
スイスを訪れたことのある方であってもその名前を聞いたことがないという人が多いことでしょう。したがって、今回はそのシュヴィーツについてのお話をさせていただきます。

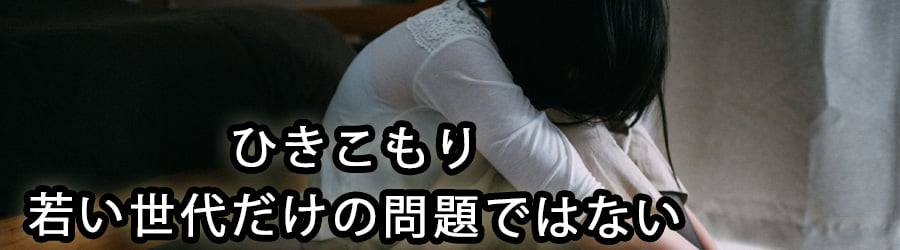
目次
ひきこもりとは、社会参加せず、自宅や自室からほとんど出てこなくなる現象と、これに該当する人のことを指します。多くは既に学生時代からひきこもりを始め、家から出なくなり、大人になっても親の家に住み続けています。きっかけは多岐にわたりますが、例えば、学校でのいじめや日本の教育制度における成績至上主義よる多大なストレスなどがあります。