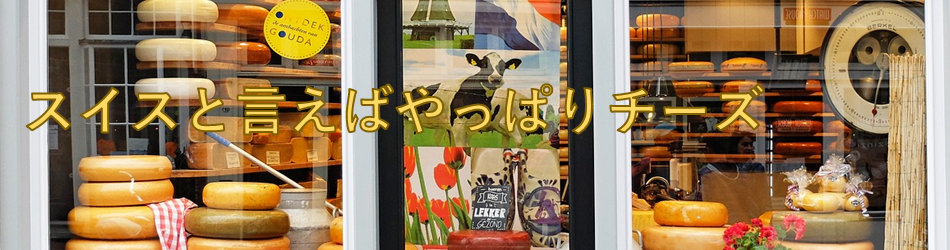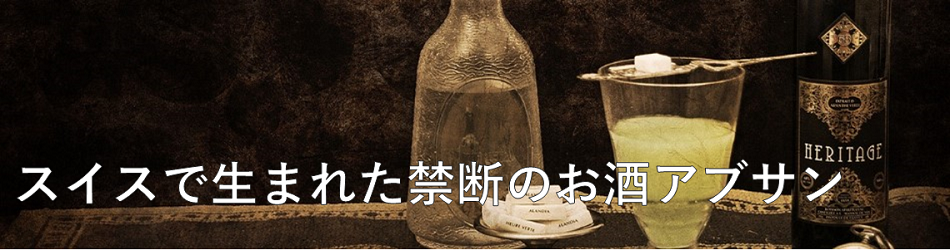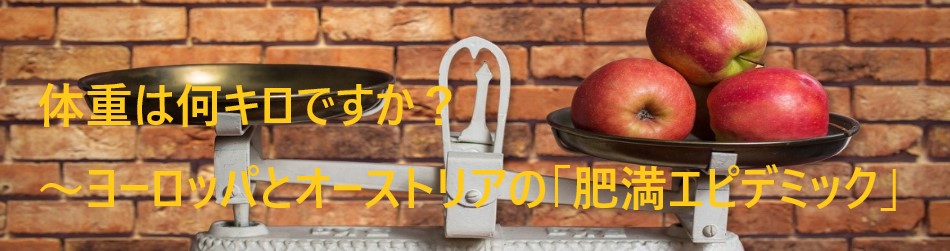中央スイスの古都ルツェルン
目次
今回はルツェルン州(Kanton Luzern)の州都で同名の都市であるルツェルンをご紹介いたします。
スイスの観光ガイドに必ず掲載されることから既にご存知の方や実際にご訪問された人も多いと思います。しかし、小さな町であるとの理由から日帰り旅行の対象にされがちで、実際にルツェルンを訪れたことのある読者様も長居はしなかったのではないでしょうか?
確かに、ルツェルンの中心部は非常にコンパクトで、短時間で効率よく回れるのですが、その郊外や周辺地域を含めば数えきれないほどの見どころに溢れています。
したがって、今回は「ルツェルンを再度訪れたい」や「一度だけルツェルンに行けるなら時間を掛けて見たい」と思えるような魅力の数々についてのお話をさせていただきます。