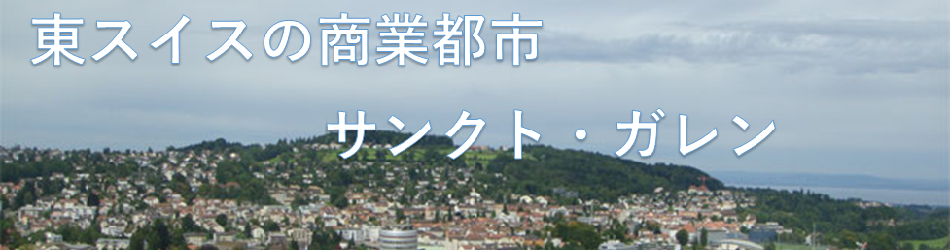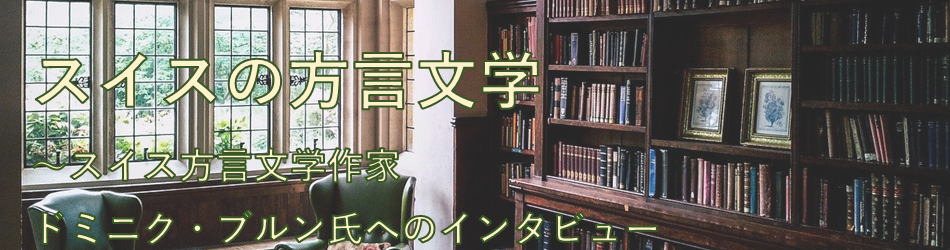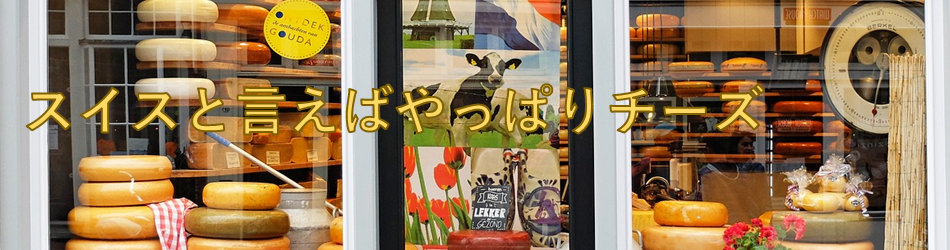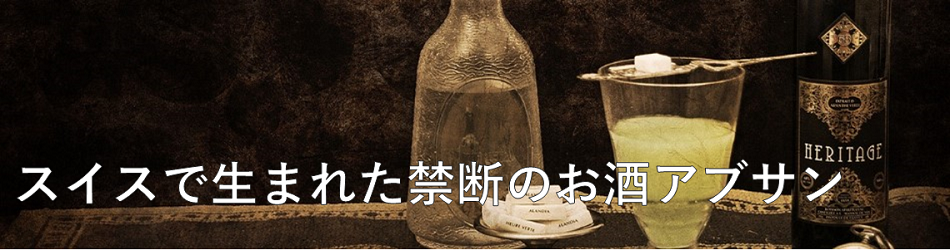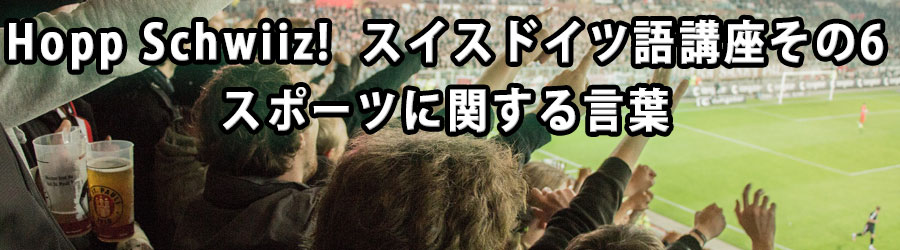東スイスの商業都市サンクト・ガレン
目次
氷河特急の旅を除けば東スイスは観光ツアーなどに含まれることはほとんどないのですが、これは決して観光名所が不足しているからではありません。
むしろ、東スイスに関しては以前にご紹介したアッペンツェルのように自然豊かで、他の地方とはひと味違う趣と個性的な文化を誇る町々が点在しますので、スイスを知る上では必ず一度は訪れる必要があると言えます。
したがって、今回はそんな東スイスの魅力溢れる文化的中心で、商業都市でもあるサンクト・ガレン州(Kanton St. Gallen)の州都サンクト・ガレンをご紹介したいと思います。