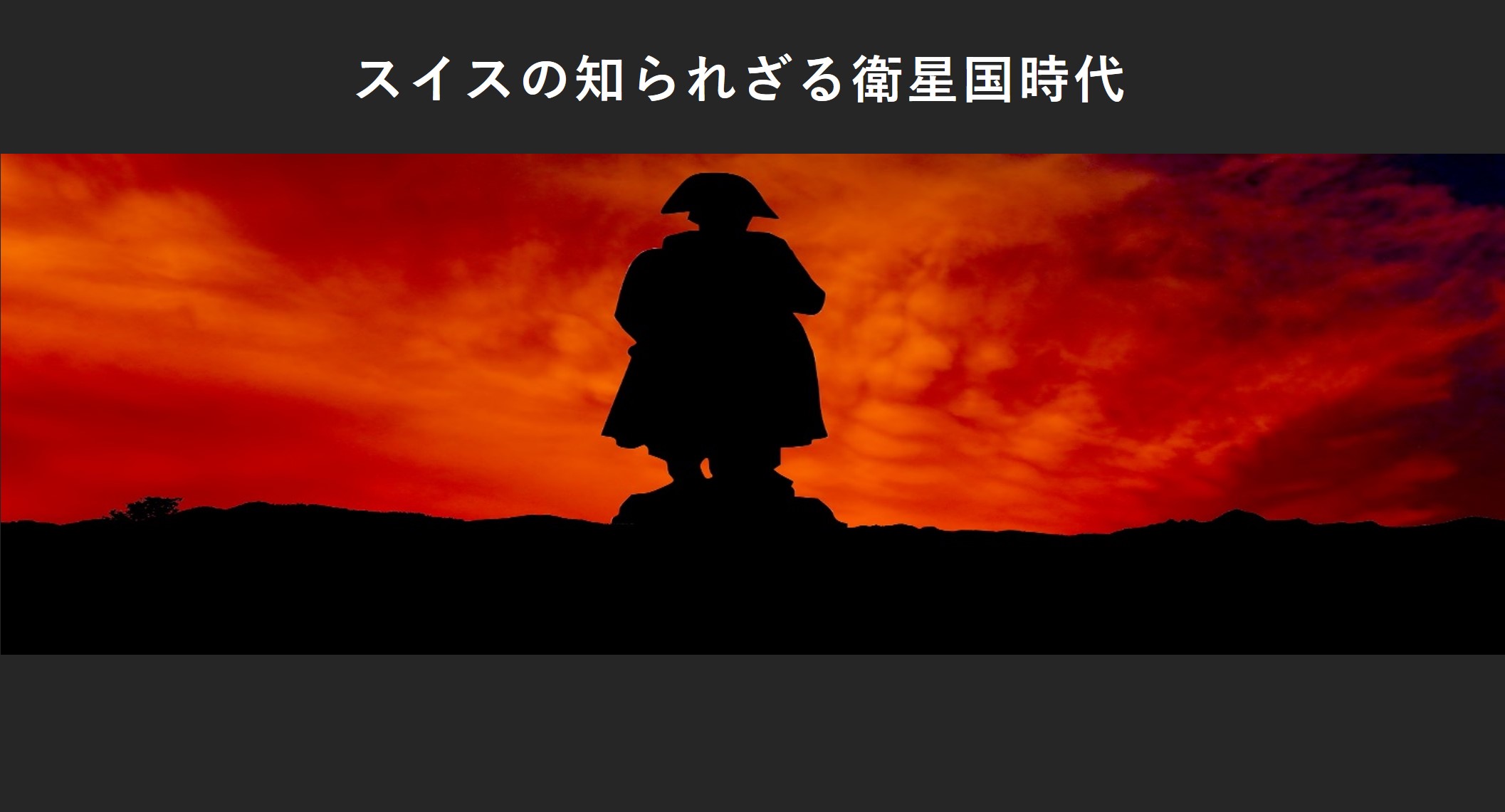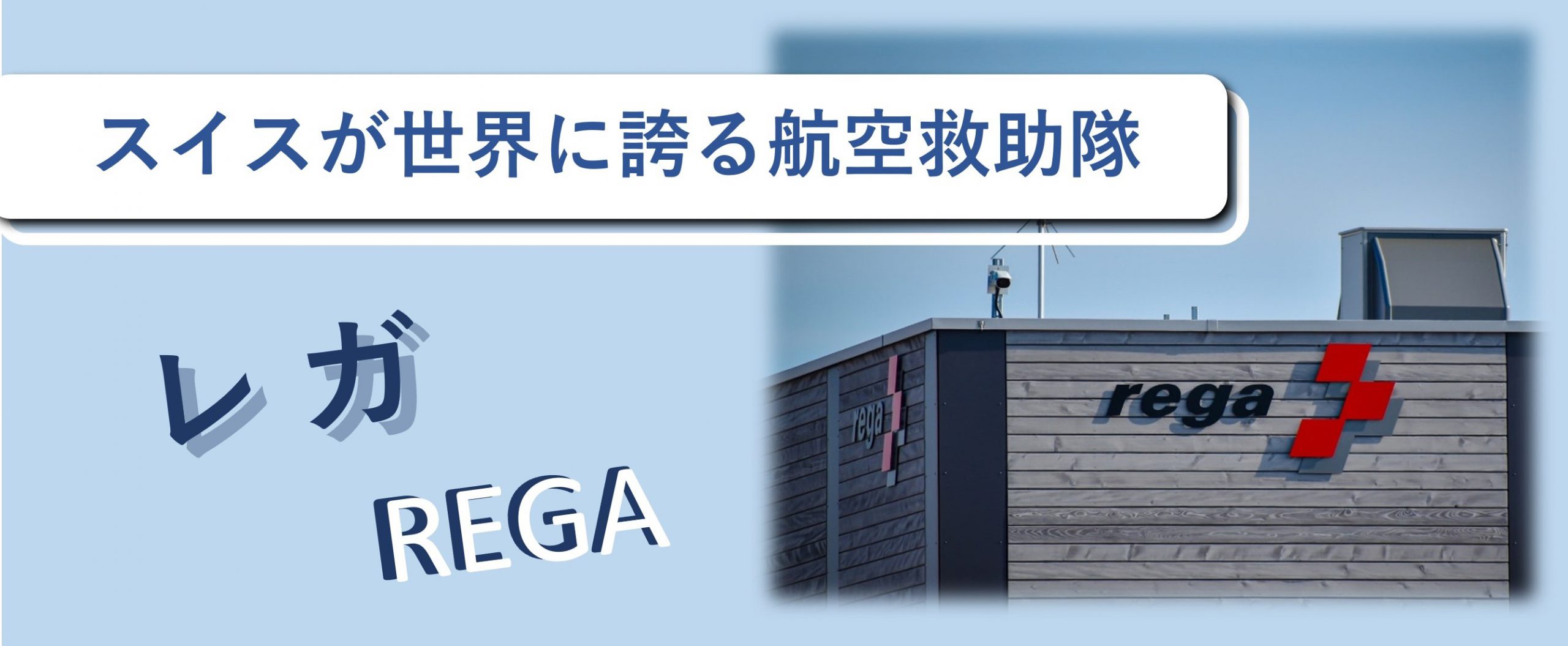東京オリンピック・パラリンピックがコロナの影響で1年も延期して開催されたこともあって、あの盛り上がりをついこの間のことのように感じている人も少なくはないと思いますが、半年後にはパリで次のオリンピックが待ち構えており、各種準備もいよいよ大詰めを迎えていますね。
それに伴い、本ブログでもオリンピックイヤーに合わせてスポーツに関する様々なネタをご紹介しようと考えております。
そして、その記念すべき第一弾としてスイスで生まれた五輪競技についてのお話をさせていただきますが、皆様はスイス生まれの五輪競技と言えばどのようなものがあるかご存知ですか?
スイスは雪国であるが故に、夏よりも冬のスポーツが盛んであるため、今回ご紹介するスポーツも当然ながら冬季オリンピックの競技になります。
名前からして「アルペンスキー」がスイス発祥の競技と思われがちですが、実を言うとアルペンスキーは北欧で生まれたとされており、残念ながらスイスを起源としていません。
一方、スイスのイメージがさほどないものの、歴史を辿ればそのルーツがスイスにあるのがなんと「スライディング競技」なのです。
したがって、今回はそんなスイス発祥のスライディング競技についてご説明いたします。
⇒続き