バイロイト音楽祭
目次
ドイツを代表する作曲家のひとりであるリヒャルト・ワーグナー(1813-1883)。数多く存在するドイツ出身の作曲家の中でも一際その存在が独特であるのは、作品にみられる思想、人々を恍惚させ陶酔感へと導くような音楽性、そしてその虜になる熱狂的なファンである“ワグネリアン”の存在などが理由かもしれません。ワーグナー自身による構想で創設された劇場で行われるバイロイト音楽祭は、今日にも脈々と引き継がれ、ドイツ文化のひとつの柱となっています。
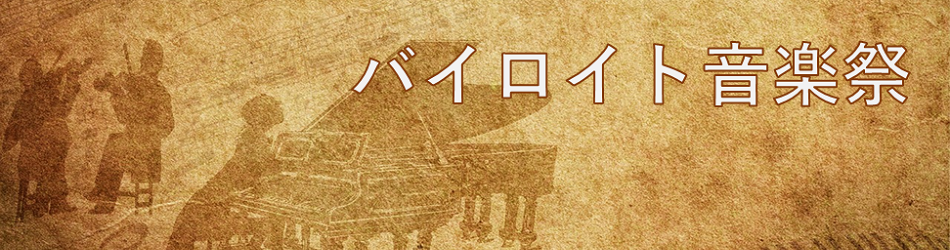

目次
ドイツの家、日本の家屋との違いは色々ありますが(ドイツの窓参照)、今回は地下室(独語:Keller)についてお伝えします。
日本の一般的な住宅ではほとんどお目にかかれない地下室ですが、ドイツではかなり一般的です。マンションのような集合住宅の場合でも、地下に世帯ごとのスペースが設けられているのも特徴的です。

目次
ぬいぐるみの定番のひとつといえばクマではないでしょうか?
そう、ドイツ発のシュタイフ社のテディベアといえば世界で一番ともいえるブランド。でもテディって一体なんのこと?どうしてドイツで生まれたのでしょう?今回はドイツ生まれのテディベアの秘密に迫ります。


目次
国章とは、国家を象徴する紋章のこと。国旗よりも複雑なデザインで、その国の風土、歴史、文化が象徴的に印されています。日本では法令上の明確な国章は定められていませんが、慣習的に、天皇家の家紋である「十六八重菊紋」がそれに準じた扱いをされています。
ではドイツの国章はご存じですか?



目次
ドイツの街に必ずある建物といえば、キリスト教の教会や大聖堂ですが、教会から聴こえる美しく荘厳なパイプオルガンの音色は、ヨーロッパ文化の真髄を感じさせます。ドイツのパイプオルガンの建造技術とオルガン音楽は、2017年にUNESCOの無形文化遺産にも登録されました。ドイツには約400のオルガン工房と、2800人の従業員が存在し、国内のオルガン台数は5万台にものぼります。ドイツは、イタリアやフランス、オランダなどと並んで、独自のオルガン文化を誇っています。

目次
ドイツで生活していると菜食主義者、いわゆるヴェジタリアンに出会うことは珍しくありません。レストランのメニューにも、野菜のみのメニューが必ずあるのも日本とは少し違うところかもしれません。さらに今日ではヴィーガンというスタイルが、欧州全体で増加傾向にあり、ベルリンでは人口の約一割がヴィーガンで、ヴィーガン食を取り扱う店も多数だとか。その食品の種類は実に豊富なドイツです。さて、そんなヴィーガン、思想的な理由から実践している人々が多いのでしょうか。また増加の理由の背景にあるのは?
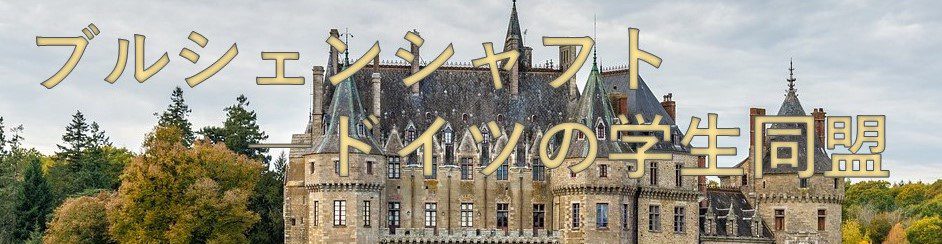
目次
サークルや部活など、日本の学校生活の中で結成されるグループ組織はドイツには存在しません。運動系のクラブは教育機関から独立したスポーツクラブ(Sportverein)がその代わりと言えます。しかし、ドイツには独自の歴史によって成立した学生同盟―ブルシェンシャフト(Burschenschaft)というものが存在します。19世紀前半に誕生したこの同盟は、近代の様々な歴史的変動や制圧を乗り越えて今日も存在しており、同盟内の規則はかなり独特で、真剣を使った「決闘」までも存在するそうです。

ブルシェンシャフトによるヴァルトブルクの祭典(1817)が行われたアイゼナハ近郊のヴァルトブルグ城