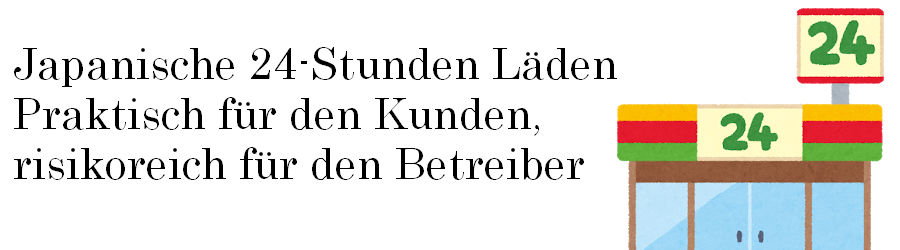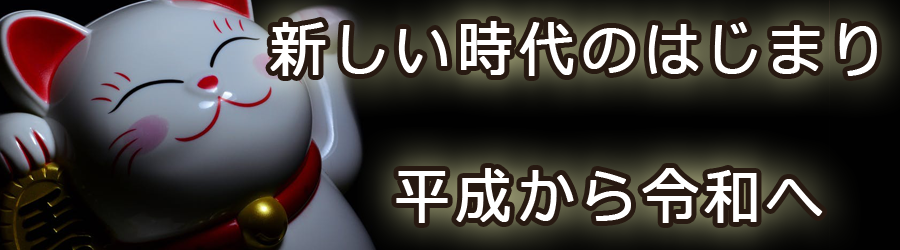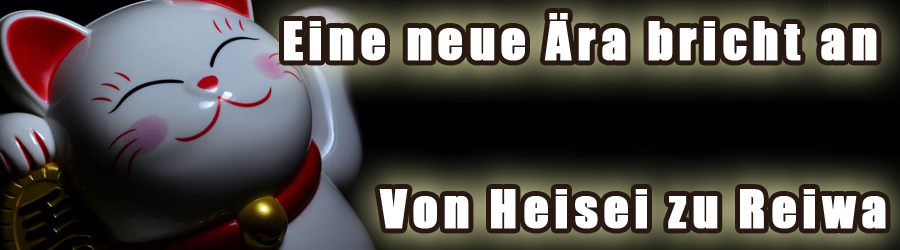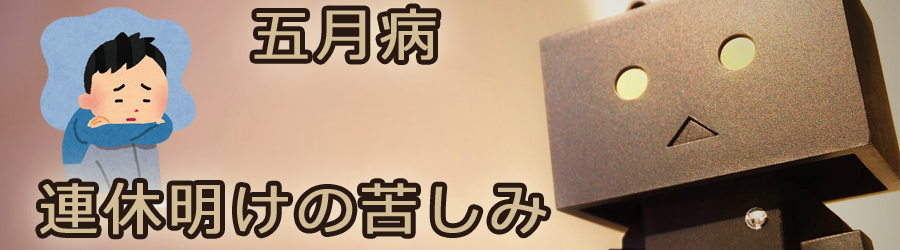Japanische 24-Stunden Läden – Praktisch für den Kunden, risikoreich für den Betreiber
目次
In Japan gibt es viele kleine Läden, die 24 Stunden geöffnet sind. Sie heißen Convenience Stores oder in der japanischen Kurzform „Konbini“. Es werden Lebensmittel, fertig zubereitete Lunchboxen, Sandwiches, Süßigkeiten, Kosmetik und andere Dinge des täglichen Bedarfs verkauft. Außerdem kann man im Konbini Geld abheben, Rechnungen bezahlen, Konzerttickets kaufen, drucken und kopieren und einige bieten auch kostenloses W-Lan an.