ドイツのお葬式に初めて参列
目次
ドイツに住み始めて20年近くなる私ですが、これまでドイツでのお葬式に参列したことがありませんでした。
しかし癌を患っていた義理の兄が先日亡くなり、初めてドイツのお葬式に参列してきました。
義理兄とのお別れは悲しかったのですが、とても印象に残るお葬式だったので、自分が忘れないようにするためにもブログで書いておきたいと思います。
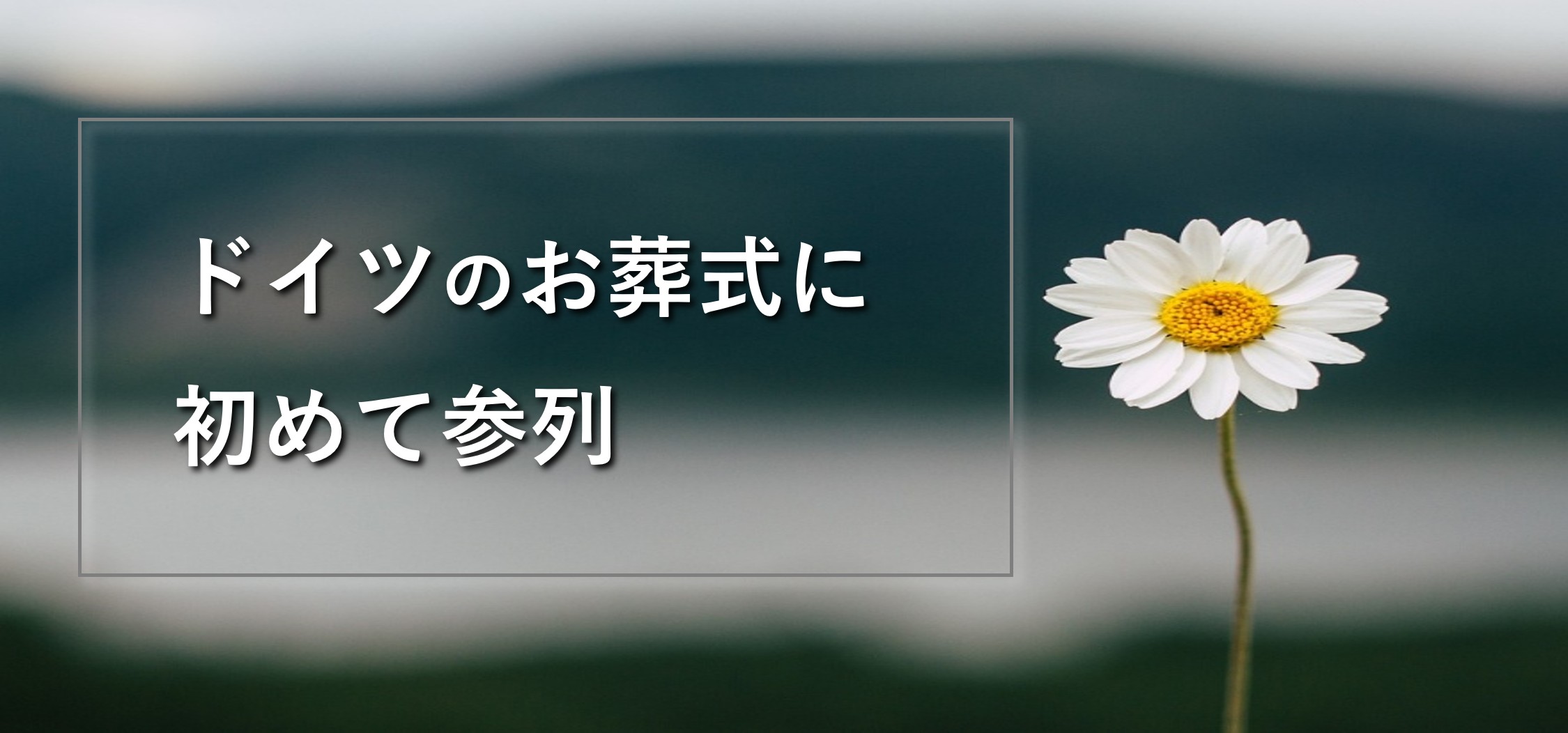
目次
ドイツに住み始めて20年近くなる私ですが、これまでドイツでのお葬式に参列したことがありませんでした。
しかし癌を患っていた義理の兄が先日亡くなり、初めてドイツのお葬式に参列してきました。
義理兄とのお別れは悲しかったのですが、とても印象に残るお葬式だったので、自分が忘れないようにするためにもブログで書いておきたいと思います。
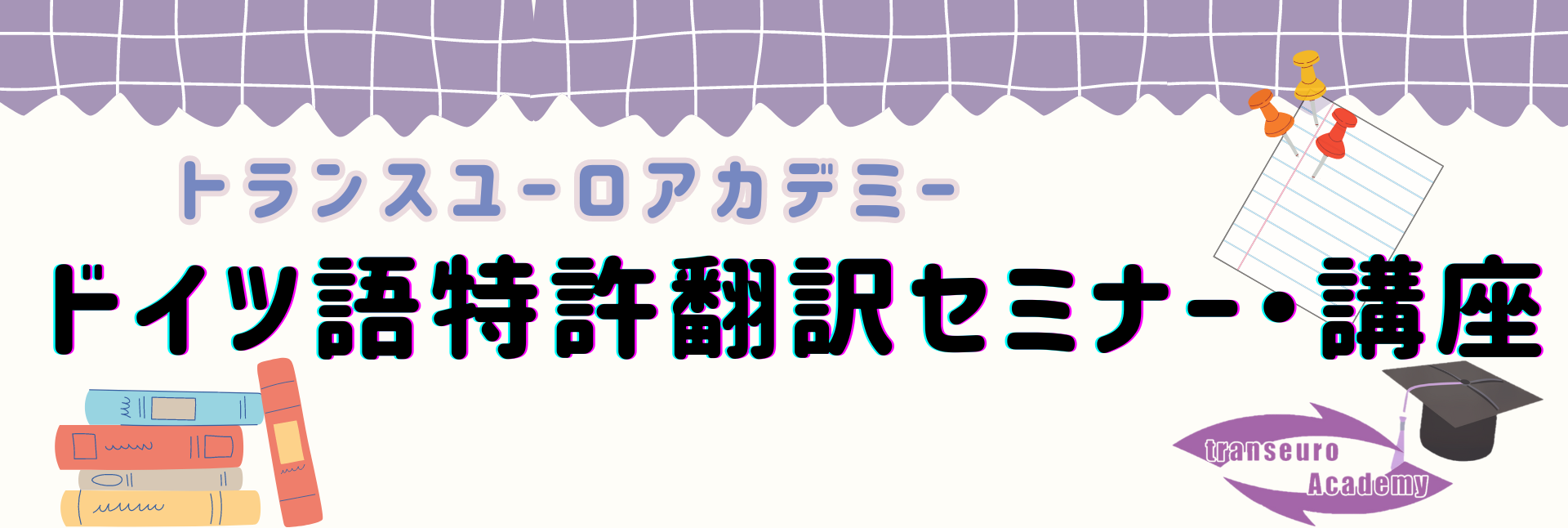
※本講座は満員となりましたので、お申し込みを終了しております。
皆様お待たせしました!!
ドイツ語特許翻訳のエキスパート・トランスユーロが運営しているトランスユーロアカデミーでは、このたび2年振りに一般コースの開講を決定しました!
現在進行中の入門コース(第7期)は、知財や法律の業務に携わっている人たちやプロの翻訳者さんなどの業界のプロの方々を始め、ドイツ語大好きな現役大学生さんなど、世代や職業を越えて国内外から多くの方々が参加してくれています。講師への質問内容など、講座中に飛び交う議論のレベルがとても高く、非常に高い意欲をもって学んでいただいています。
この入門コースは2025年3月で最終回を迎えますが、この勢いに乗って、入門講座の終了後にすぐに一般コースをスタートさせます!

目次
皆様お久しぶりです!
今までかなりの頻度でスイスドイツ語講座を行ってきましたが、実は先日重要なことに気付いてしまいました。
本講座ではなるべく実用的なスイスドイツ語を中心に、色々な場面で使用できる言葉をご紹介することを心掛けているものの、使う回数が最も多いと言っても過言ではない感謝の表現を教えていませんでした。
感謝は仕事、私生活を問わず対人関係において決して忘れてはならないもので、それをするのとしないのとでは周りの人の印象を大きく左右する一番大切な感情表現です。
したがって、今回はスイスドイツ語をマスターする気がなくても、観光でスイスを訪れたり、どこかでスイス人と遭遇したりした際のために知っておくべき感謝の言葉について色々とご説明させていただきます。
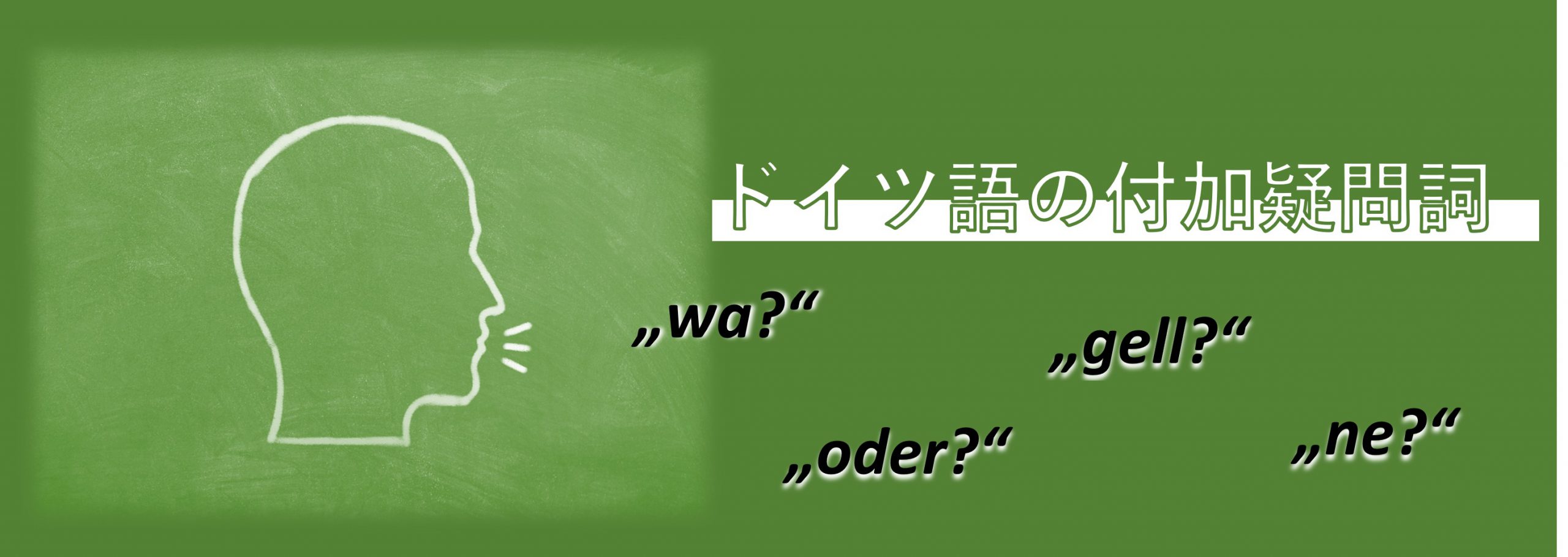
目次
こんにちは。皆様素敵なクリスマスを過ごされたでしょうか?
このブログも今年の夏に書き始めて第四回目を迎えることとなりました。
私のドイツ語をめぐる経験談を、専門であるドイツ語諸言語学の観点から専門的になりすぎないくらいに記事として書き、興味をお持ちの皆様にこうしてお伝えするのはとても楽しく、読んでくださった知り合いの方々からも「これからも楽しみにしているよ!」と、たくさんの温かい声をかけていただいております。本当に励みになります。ありがとうございます。


目次
以前、スイスには「首都」がなく、ベルン(Bern)を連邦機関の所在地として「連邦都市」と定めていることをご説明させていただきましたよね?
スイスが元々国家連合として設立されたことから、連邦州の平等性を維持するためにあえて首都を定めず、各州の代表者が集会する場所をローテーション制で毎年変えていました。
そして、1848年に国家連合から連邦国への改革を行った際にひとつの州に政治的な優勢性を持たせず、全州の平等性を引き続き確保する解決策として生まれたのが「連邦都市」の制定でした。
とはいえ、過去を振り返るとなんとスイスにも一時的に「首都」が存在していた期間があったのです。
この事実は国外ではあまり知られていませんが、スイス人にとっては自国の歴史を知る上では重要な1ページと言えます。
したがって、今回はアールガウ州(Kanton Aargau)の州都であり、スイス初の首都でもあったアーラウ(Aarau)をご紹介させていただきます。

目次
あけましておめでとうございます、2025年の幕開けです。
毎年恒例となって参りましたが、今年もまずはドイツ語協会(GfdS)が選んだ2024年のドイツの流行語大賞についてお伝えします。(2023年の流行語大賞、2022年の流行語大賞)2024年もドイツは政治的にも社会的にも多くの課題を抱えていました。それは流行語にも表れています。
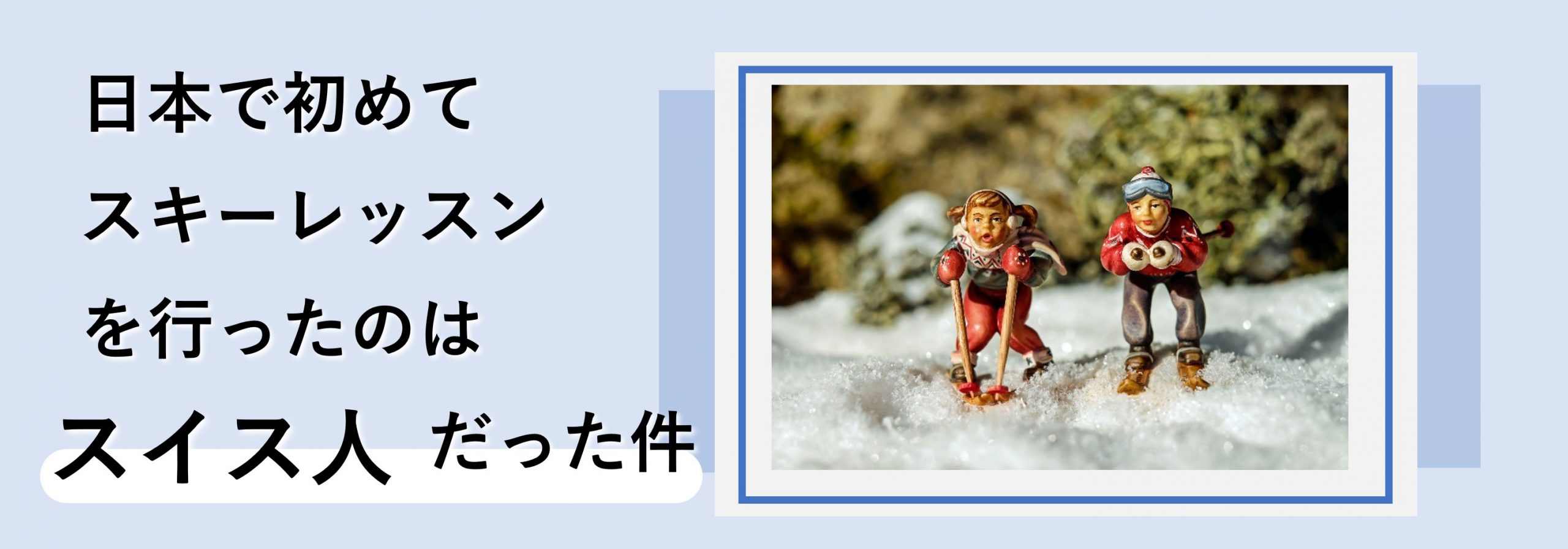
目次
12月になって今年ももうあと僅かのところまでやってきました。
年末と言えば忘年会やクリスマスに加え、大掃除も控えていることから、何かとバタバタする時期ですよね?
また、気温も下がって、風邪を引かないように体調にも気を配る必要がありますので、冬はどちらかというと苦手な方も少なくはないと思います。
しかし、ウィンタースポーツを楽しむ人にとっては逆に待ち望んだ季節で、これからが本番であると感じているのではないでしょうか?
雪国であるスイスにおいてはスキーやスノーボードが国民的なスポーツと言えるほど人気で、冬が嫌いな人を含め、国民の殆どが恒例行事のように最低でも年に一回はゲレンデに足を運ぶのが普通です。
それに対して日本では地域差があるものの、ウィンタースポーツを一切しない割合が意外と高い印象を受けます。
生まれ育った場所が雪の降らない沖縄か積雪が数メートルにも及ぶ北海道かで、ウィンタースポーツとの関わり方にも大きな違いが生じるのは無理もありませんし、スポーツは個人で好き嫌いが分かれますが、競技人口がもう少し多くてもいいのではと感じます。
因みに、日本でスキーと言えば、日本において初めてスキーレッスンを行ったのはスイス人だったことをご存知でしたか?
この事実は今から100年以上も前の出来事で、教科書にも掲載されていないことから知らない方も多いと思いますので、今回はとあるスイス人も大きく関与している日本のスキーの歴史についてご説明させていただきます。

目次
私がドイツ人の夫と結婚して義理の母から教わった最初のドイツ菓子が、クリストシュトーレンでした。
彼女のお母さんが、その昔一流ホテルのレストランで料理人をしていたらしく、毎年12月になると当時のレシピでシュトーレンを焼くのが彼女のクリスマス前の習慣だったそう。
私も当時のクリストシュトーレンのレシピを教えてもらって、毎年クリスマス前にシュトーレンを焼くようになりました。今回は、我が家に伝わる秘伝のレシピを紹介したいと思います!

目次
先月ノーベル賞の受賞者が順次に発表され、以前からノミネートが期待されている村上春樹さんの受賞は今回も実現しなかった一方、平和賞が日本被団協に贈られると決まったことに驚いた人も多いのではないでしょうか?
日本人によるノーベル平和賞の受賞は50年ぶりの出来事ですが、過去を振り返ると山中伸弥教授や吉野彰博士をはじめ、特にこの25年間で数多くのノーベル賞受賞者を輩出してきた実績があり、さほど異例なことでもないかもしれません。
また、そのような背景から日本国民の間でノーベル賞に対する関心が年々高まっており、皆様の中にも今年の受賞者が気になってその発表に注目した方が少なくないと思います。
しかし、大半の人はあくまで自国の人物がノーベル賞を受賞するか否かに着目しており、他国の受賞者にはさほどの興味がないように感じます。
というのも、ノーベル賞を受賞したスイス人を聞かれると、日本では殆どの方が一人も答えられず、稀に1人か2人の名前を知っている人がいるのが現状です。
また、そもそもノーベル賞を受賞したスイス人が過去に存在したのか分からない方まで僅かながらいますので、スイス人である私にとっては非常に悲しい現実に直面しております。
そこで、今回は日本人以外のノーベル賞受賞者に関する一般的知識を広める目的で、過去にノーベル賞を受賞したスイス人についてご説明させていただきます。